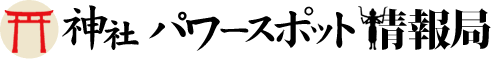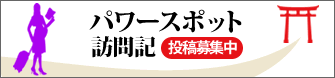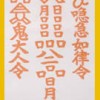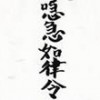赤間神宮(あかまじんぐう)
赤間神宮は、壇ノ浦の戦いで入水、わずか8歳で亡くなった安徳天皇と、平家一門を祀った神宮で、まるで竜宮城のように華麗な姿です。
なぜ竜宮城のような姿かと言うと、安徳天皇の祖母であった二位の尼という方が、幼い孫を抱いて入水するという時に「きっと海の中にも都はありましょう」と語ったという話から来ているのだそうです。
そして毎年5月の安徳天皇の命日に行われるのが「先帝祭」という祭事で、いにしえにタイムスリップしたかのような、美しい平安装束の行列を見ることができます。
しかし実は赤間神宮は怖い体験(霊を見たとか)も多く耳にするスポットで、特に夜間は足を踏み入れない方が無難なようです。
平家の方々をお祀りしているということは、やはり無念を抱えて亡くなった人ということになりますし、今でこそ赤間「神宮」となっていますが、江戸時代までは安徳天皇御影堂、つまり安徳天皇を供養するためのお寺だった場所です。
そういう意味では、元から神をお祀りしている神社とは少し成り立ちの違う「神宮」なんですね。
赤間神宮の詳細情報
赤間神宮の主なご利益・こぼれ話
・開運招福
・家内安全
・子宝安産
・諸願成就
・航海安全
・国家鎮護
所在地
山口県下関市阿弥陀寺町4-1 (HP)自宅でいつでも気軽に試せる電話占い

恋の悩み、仕事の悩み、人間関係の悩みなど、なかなか周囲には吐き出せない想いを抱えている方に最近人気なのが、電話占いです。
電話占いとはその名の通り、自宅にいながらにして凄腕の占い師に相談できるシステムのことで、算命術や占星術、タロット、透視鑑定などを通じて、恋の行方や願望が叶うかどうかを占う仕組みになっています。
しかしこの電話占いがブームになってからというもの、雨後の竹の子のように様々な鑑定所が出来ていますが、しっかりと真面目な鑑定所を選ぶ目安として、以下のことをチェックしてみてください。
(1)無料でお試し占いが出来るかどうか?
(2)実績ある占術師が在籍しているか?
(3)しつこく追加サービスの勧誘等がないか?
そしてこれらを踏まえた上でのおすすめは「電話占いピュアリ![]() 」という鑑定所です。
」という鑑定所です。
まず(1)については10分間の無料お試し占いが出来るので、自分に合う占い師さんを、無料で見極められるようになっています。
そして(2)については、「電話占いピュアリ![]() 」は、全国的に有名な占い館(千里眼、沖縄アクアマリン、金魚堂、ほしよみ堂)と提携関係にある、数ある電話占いの中でも珍しい所です。
」は、全国的に有名な占い館(千里眼、沖縄アクアマリン、金魚堂、ほしよみ堂)と提携関係にある、数ある電話占いの中でも珍しい所です。
こういった有名どころの占術師さんが、いかがわしい所と提携を結ぶことはないと思いますので、その点でも信頼が置けます。
最後に(3)については、中には「悪い運を払拭するために除霊する」などと言って、高額な祈祷料を要求したり、何かとこちらの不安につけ込んで、オプションサービスを売りつけるような所が稀にあるようですが、ピュアリはこの点もクリーンで安心出来るということです。
しかし実際、どんなことが行われているのか?興味のある方も多いと思いますので、実際に電話占いを体験した方の感想を紹介します。
試してみたいという方は、参考にしてみてください。
全国の実力派占い師が待機中!初回鑑定10分無料の「電話占い ピュアリ」>>![]()
悩みを打ち明けられて、気分がすっきり(H.Aさん)
気が滅入っている時など、雑誌やテレビの占いを見ると
気持ちが落ち着く時があります。
私は占いというものは、よい事だけを信じる様にしています。
昨年になりますが、友人との会話で占いの話になり
電話占いが良いという話になりました。
私も興味がありましたので、ネットでいろいろ調べてみると、友人の言う通り
電話占いはここ数年でかなりの人気が出ているようでした。
又、多くのサイトに無料鑑定があり、物は試しにと一度占って頂く事にしました。
電話占いを行なう上でのメリットとしては、対面占いとは違い、
お互い顔が見えないので、ある意味相談しやすい事で、
面と向かっては言いにくい事でも、案外何でも気軽に相談できました。
元々、知らない人と話をするのは苦手な私ですので、
この占い方式は良かったです。
又、私の占った所は最初の10分は完全無料で行なってくれるということで、
それも電話占いを利用した動機でもあります。
それに自宅から簡単に利用できるのもリラックスできて良い点です。
ちなみにこの電話占いでの的中率は半々といったところで、むしろ、
何かを予言するというよりも、これからの行動のアドバイスが強い印象でした。
ですから占いというよりも、お悩み相談みたいな感じの印象でしたが、
おかげで気持ちが前向きになれた事は確かでしたので、
利用した価値はあったと思います。
電話占いは、自宅にいながら簡単にできますので、忙しい方や、
対面占いに抵抗のある方にはおすすめできると思います。
関連記事
-

-
大神山神社(おおがみやまじんじゃ)
大神山神社は鳥取県にある神社で、中国地方屈指の霊峰と言われる伯耆大山の麓に座しており、平安時代には修
-

-
八重垣神社(やえがきじんじゃ)
八重垣神社は島根県松江市にある神社で、縁結びと鏡の池の占いで有名なお社です。この八重垣神社は素戔嗚尊
-

-
厳島神社(いつくしまじんじゃ)
厳島神社は水に浮かぶ大鳥居が印象的な、広島県にある神社です。私は学生時代に修学旅行で行って「水に浮か
-

-
金持神社(かもちじんじゃ)
金持神社は鳥取県に位置している、名前からしてお金持ちになれそうな神社です。毎年ジャンボ宝くじのシーズ
-

-
須佐神社(すさじんじゃ)
須佐神社は島根県出雲市にある神社で、その名の通り、須佐之男命(すさのおのみこと)をお祀りしている神社
-

-
延命地蔵堂(えんめいじぞうどう)
広島県呉市にある延命地蔵堂は、不思議な言い伝えが多く残るお地蔵様です。天保の飢饉の際、多くの災害によ
-

-
出雲大社(いずもたいしゃ)
言わずと知れた「縁結び」の大本命が、島根県にある出雲大社です。ここは参道からしてとても立派で、玉砂利
-

-
吉備津神社(きびつじんじゃ)
吉備津神社は岡山県にある神社で、桃太郎伝説にゆかりのある神社として知られています。桃太郎の話に登場す
- PREV :
- 厳島神社(いつくしまじんじゃ)
- NEXT :
- 大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ)